
記憶を強化し成功へと導くのは、失敗と、それに対するたゆまぬ前向きな工夫と繰り返しです。
記憶は、失敗によって深まる
最近の脳科学の研究にほると、記憶は「失敗」と繰り返しによって強化されると考えられています。したがって、失敗が多いほど記憶は正確で強固なものとなるのです。
失敗しても常に前向き次に打つ手を考える、そのポジティブな姿勢が、厳しい自然の中で人類が生き残るために必要だったのです。失敗について落胆してくよくよとしている暇は、いきていくためになかったのです。
脳の記憶はおおざっぱでいい加減である。だから応用力がきく。
どんどん変わる自然という環境の中で、人間は過去の「記憶」を頼りに、様々な判断をしながら生きる必要があります。しかし、過去と全く同じ状況は2度とありません。だから、記憶は程よい曖昧さ、言い換えれば「柔軟さ」が必要とされるのです。
もし記憶が厳密だったらどんどん変わっていく環境のもとでは、活用することのできない無用の長物になってしまうかもしれません。ゆえに、記憶は適度に曖昧で柔軟なことが大切なのです。
例えば、ひとはそれぞれ字の特徴、すなわち筆跡が異なります。にもかかわらず同一の文字かどうかが見分けられるのは、この曖昧さ柔軟さのおかげです。また、知っているひとが違う格好をしていても同一人物と見分けられるのも、記憶の適度な曖昧さのおかげで、応用範囲が広げっているのです。
ゆえに、脳は、いきなり細かいことを正確に覚えても応用が利きません。まず大きくものごとを捉えて理解することができたのちに、小さい区別ができるようになるのです。
これは、我々が勉強して何かを習得しようとするときにもあてはまります。初めは細部を気にしないで、おおまかに理解することが大切です。細かいことは、その後で少しづつ覚えていったらいいのです。
断片的知識はすぐに記憶から排除される。まず大局を捉えよう。
例えば日本史を習うときのことを想定してみます。このときある時代の細部をいきなり覚えようとするのは合理的ではありません。
仮にそうして、ある部分が理解できたように思えてもそれは理解の浅い知識にすぎません。全体から切り離されて断片的で役にたたない知識です。そんな知識は脳の中からすぐに排除されてしまいます。
そうならないために大局的な歴史の流れをしっかり理解し、その流れの中に細部の知識を位置づけていくことが大切です。
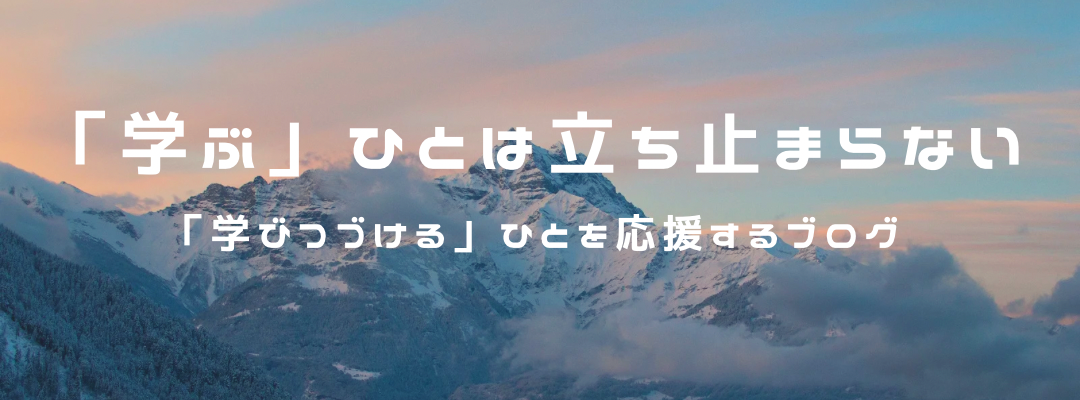



コメント